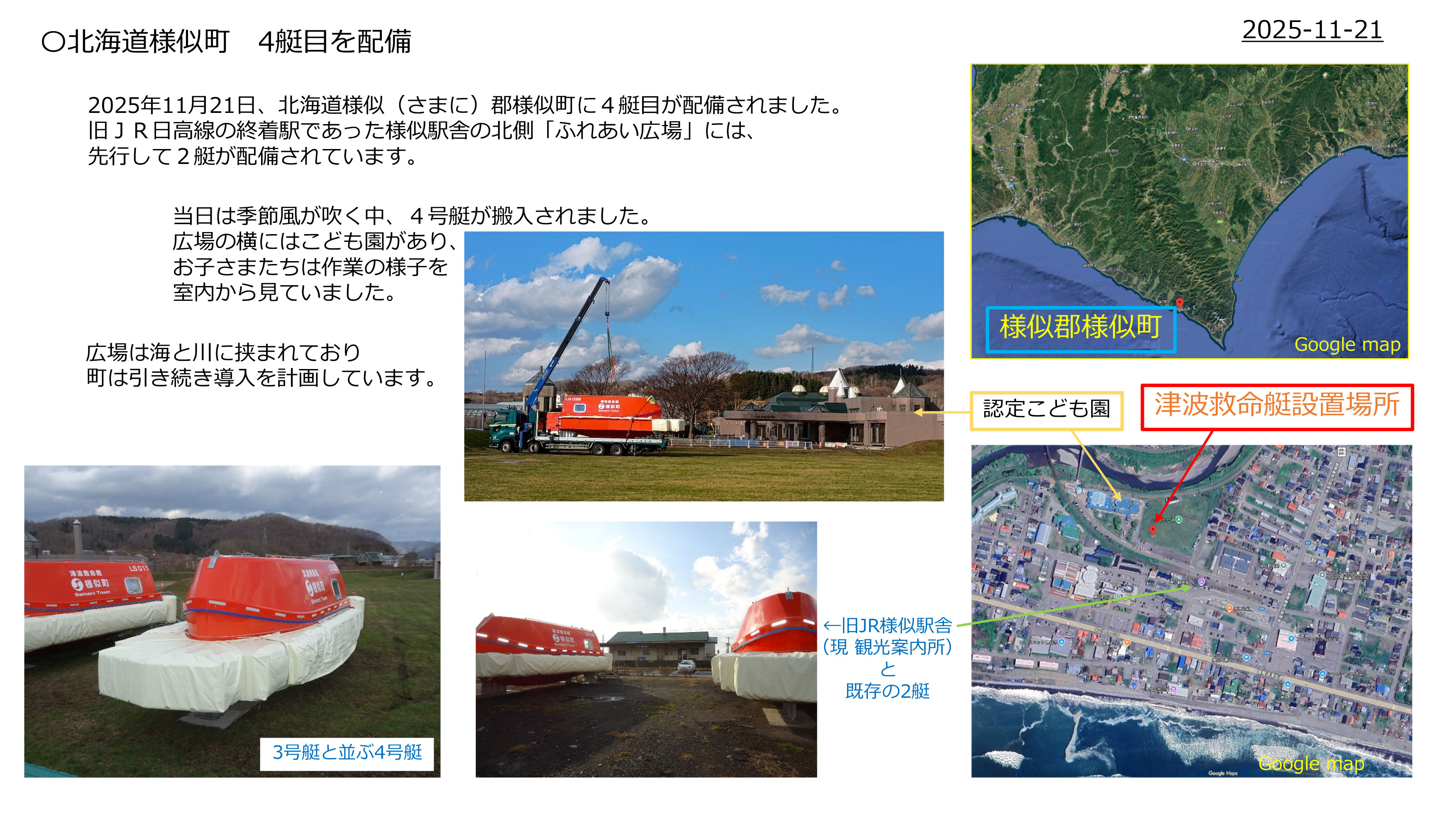(風景写真など:北海道浜中町提供)
背景
2011年3月に発生した「東日本大震災」では、地震に加え巨大な津波が発生し、東北地方の太平洋岸を中心に甚大な被害をもたらしました。
高台などへの速やかな避難が困難なケースも多数発生し、また、高齢者等のいわゆる避難弱者といわれる多くの方も犠牲になられました。
こうした教訓を踏まえ、津波の破壊力に対しても壊れることがない、強靱で中の人を安全に避難させることのできる津波避難用の救命艇(津波救命艇)が国土交通省により考案されました。
なお、従来から津波の際に浮いて避難することを目的とした様々な器具が販売されていますが、それらが十分な安全性が確保されているか、判断するための基準がありませんでした。そこで、国土交通省は津波救命艇が備えるべき性能要件等を示した「津波救命艇ガイドライン」を平成26年9月に策定し、安全性を判断するための基準等を公表しました。
東日本大震災から十数年が経った今、改めて津波の脅威に備え、記憶の風化と戦いながら津波への備えを怠らないことが重要です。
しかしながら、津波救命艇は現在全国に45隻(令和7年4月時点)が設置されている状況にあります。そのため、多くの助けられる命を助けられない状況にあると言わざるを得ず、「津波救命艇ガイドライン」を満足する安全・安心な津波救命艇の普及が急がれています。
津波救命艇とは
津波救命艇は、東日本大震災の教訓を踏まえて国が定めた安全基準(津波救命艇ガイドライン)を満足する、津波避難用の船です。
津波の中に放り出されれば、大量の「がれき」によって大けがをしたり、冷たい海水によって体温を奪われ、生き延びることはとても難しいといわれています。津波の威力は凄まじく、通常の船やボートでは津波に巻き込まれることはとても危険です。
津波救命艇は十分な強度がある上に、海水が中に入ってくることもありません。東日本大震災では、巨大津波により、高台などにたどり着くことのできなかった多くの方々の尊い命が失われました。もし、住まいの近くに津波救命艇があったら、どれだけ多くの命が救われたことか知れません。
また、避難が困難な高齢者や身体の不自由な方などにとって、津波救命艇は有効な避難手段になると期待されています。
○ 大きさは、長さ約9m、幅約3mとコンパクトで中型バス程度です。
詳しくはパンフレットへ



津波救命艇の普及を進める会の設置
津波救命艇の普及を促進するための横断的な枠組みとして、「津波救命艇の普及を進める会」(代表:丸山研一)が2022年(令和4年)2月11日に発足しました。
津波救命艇の普及を進める会では、津波救命艇の周知啓発に努めると共に、調査等を実施してその普及を図るとともに、津波救命艇を安全に長期間にわたり使用可能な状態で維持するための管理方法の指導や津波救命艇を用いた避難訓練のサポート等を行っています。
活動等
具体的には以下の活動を⾏うこととしています。
- ① 津波救命艇の情報の発信
- ② 自治体、沿岸地域の諸施設、住民等への啓発活動
- ③ 津波救命艇に関する問い合わせへの対応
- ④ 講演会、説明会等の企画及び協力
- ⑤ メンテナンスに関する助言等
- ⑥ 津波救命艇を用いた避難マニュアルの策定や訓練への協力
- ⑦ その他津波救命艇やその普及に係わる活動
安全性の確保
津波救命艇の安全性については、国土交通省が、国民が適正な津波救命艇を選択できる環境を整え、もってその円滑な普及に資することを目的として、2014年(平成26年)9月に「津波救命艇ガイドライン」を策定しています。その中で、本ガイドラインの要件を満たしていることについては、第三者機関による評価を受けることが推奨されており、現在その評価は、一般財団法人 日本舶用品検定協会が行っています。
本ガイドラインに基づく厳格な試験の様子は、本ホームページでご覧になれます。
国土交通省海事局の「津波救命艇ガイドライン」に基づく評価を受けた津波救命艇の製造者は3社ありますが、現在はそのうち上記写真の2社((株)信貴造船所、ツネイシクラフト&ファシリティーズ(株))のみが製造を行っています。両社のHPは関係機関リンク先のとおりです。
津波救命艇について安全性などの全貌をご紹介
(信貴造船所:前半12分21秒)
(ツネイシクラフト&ファシリティーズ:後半7分18秒)
遭難信号発信装置でどうして助かるの?

○ 遭難信号発信装置の適正な使用方法
※艇内に掲示して下さい(A4でカラー印刷してラミネート加工すると良いです)
衝突強度試験をご紹介
自己復原試験をご紹介
津波救命艇の維持管理
津波救命艇は、何時発⽣するか分からない津波襲来時に、避難者を確実に安全に助
けることが絶対の使命です。
〇 津波救命艇のガイドライン(国⼟交通省)の「維持・管理の⽅法」には、
製造者が⽰す維持管理マニュアルに従い、定期的に点検し、津波救命艇の品質、性能の維持に努めること。製造者(または製造者から要請された者)は使⽤者に対し、必要に応じ適切にアドバイス等を⾏う。使⽤者が定期点検整備を製造者等に委託することもできるが、その場合も使⽤者が⽴ち会うこと。
なお、定期点検整備に加えて、使⽤者は津波救命艇の機能が維持されていることについて、第三者機関※による確認を受けることが推奨される(概ね5年毎)。
と記載されています。
避難者を確実に安全に助けるためには、上記のとおり津波救命艇の使⽤者( 管理者)が定期的に点検することが極めて重要です。
津波救命艇は⼀般的に海岸近くに設置されていますから、例えば、ドアやレバーの固着で艇内に⼊れなかったということになれば、管理者の責任問題ということにもなりかねません。
基本としては、1ヶ月に1度簡単な点検を⾏い、1年に1度詳しい点検を⾏うことです。なお、同ガイドラインでは概ね5年毎には、専⾨家による確認※を薦めています。
津波救命艇の維持管理担当者の参考として、「毎月の点検表 」と「毎年の点検表
」と「毎年の点検表 」を作成しました。点検時にご活⽤いただければと思います。
」を作成しました。点検時にご活⽤いただければと思います。
なお、既に製造者が作成した「維持管理マニュアル」や、⾃ら作成されたマニュアルに従い点検をされている場合には、そのまま継続してください。なお、⾃ら作成されたマニュアルを使⽤されている場合には、当会作成の点検表を参考にして不⾜があるようでしたら修正をお願いします。
(※) 確認の実施機関:(⼀財)⽇本舶⽤品検定協会
〇 維持管理事項 毎月の点検用
〇 維持管理事項 毎年の点検用
トピックス
トピックスアーカイブ
トップ写真アーカイブ
- 北海道泊村
- 北海道島牧村